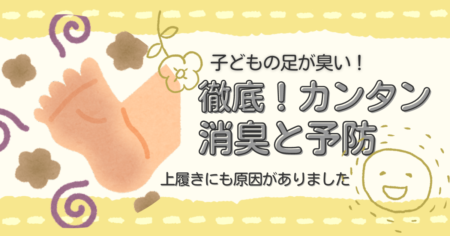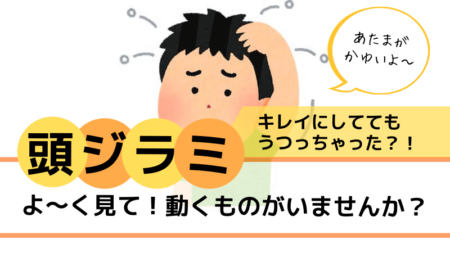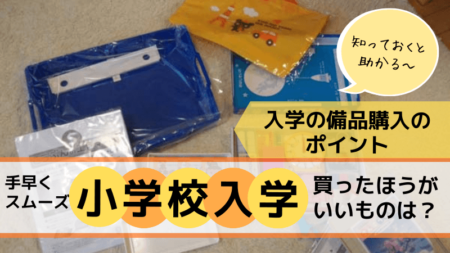小学校の図工で必要になったタンポの100均の材料を使った簡単な作り方をご紹介します。
タンポとは、わかりやすく言うと、布に綿(わた)を詰めた、てるてる坊主のような状態のものです。
図工でお絵かきのときに、タンポに絵の具を染み込ませて、紙などにポンポンと押し付けて色をつけるためのものです。
作り方は簡単で、100均の材料でも作ることができます。
私が実際に作った方法をご紹介しますね。
参考にしていただければうれしいです。
図工で使うタンポとは?
それにしてもたんぽとは?ちょっと調べてみました。
タンポは、拓本を採るときに墨をつけて叩く道具である。書や絵をかくときの筆に当たる。漢字では「短穂」あるいは「打包」と書く。後述するように綿を丸めて球状にするところから、語感が似たタンポン(綿球)に由来する語と誤解されることがあるが、両者の間には特に関係ない。(Wikipediaより)
わかりやすく言うと、布に綿(わた)を詰めた、てるてる坊主のような状態のものです。
図工でお絵かきのときに、タンポに絵の具を染み込ませて、紙などにポンポンと押し付けて色をつけるためのものです。
100均の材料を使ったタンポの簡単な作り方
学校からのお知らせには下記のようなたんぽの作り方が一応書いてありました。
「いらない布に綿(わた)を詰めて直径10cmくらいの団子状にして、輪ゴムで縛り付ければ出来上がりです」
ということなのですが、私は一度大失敗したので(中に布を小さく切ったものを詰め込んでしまった)、成功した作り方をご紹介します。
たんぽ作りで使う100均の材料
タンポは100均の材料で簡単に作ることができます。
材料(すべて100均にあります)
- 綿(わた) 20センチ角くらい
- 布またはガーゼ(家にあるいらなくなった綿100%のTシャツでもいいです)
- 輪ゴム
たんぽの簡単な作り方
たんぽの作り方をご説明します。
たんぽの作り方
- 100均で買った、または着られなくなったTシャツ(綿100%)などの布を切る
(たんぽ1個分は前後どちらかの見頃の4分の1程の大きさに四角に切ります) - 綿(わた)をギュッと包んで輪ゴムでギュギュっと縛り付ける
- あまっている部分の布を切り取る
あっという間にできました。
注意点
1・たんぽの外側の布も100均で手に入りますが、着られなくなった綿100%のTシャツなどでも十分です。
2・中に詰める綿(わた)はクッションなどに詰める用のものなのでフワッとしています。
なるべくギュッとこれでもか!くらいに詰めたほうがいいです。
3・あまっている布部分は、タンポを使うときに手に持ったり握ったりする部分になるので、ちょっと多めに残したほうがいいかもです。
一度の失敗のあとうまく作れるようになったので、次回はまかせて!と思っていたのですが、その後たんぽが必要になることはなかったです・・
図工で必要なタンポとは?100均の材料を使った簡単な作り方まとめ
図工で必要なタンポとは?
わかりやすく言うと布に綿(わた)を詰めた、てるてる坊主のような状態のものです。
図工でお絵かきのときに、タンポに絵の具を染み込ませて、紙などにポンポンと押し付けて色をつけるためのものです。
タンポは100均の材料で簡単に作ることができます。
材料(すべて100均にあります)
- 綿(わた) 20センチ角くらい
- 布またはガーゼ
- 輪ゴム
たんぽの作り方
- 着られなくなったTシャツ(綿100%)を切る(たんぽ1個分は前後どちらかの見頃の4分の1程の大きさに四角に切ります)
- 綿(わた)をギュッと包んで輪ゴムでギュギュっと縛り付ける
- あまっている部分の布を切り取る
たんぽ作りの参考にしていただけるとうれしいです。
最後までお読みいただきありがとうございました。