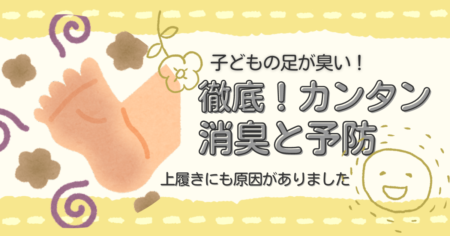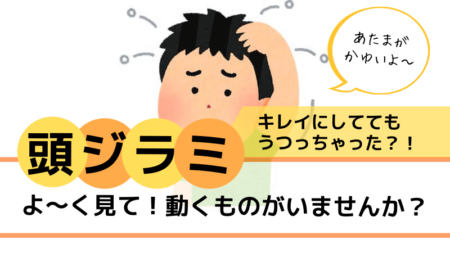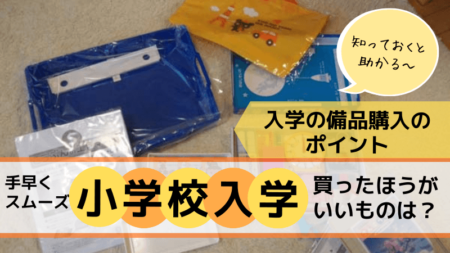娘が小学1年生の時に学校からのお知らせで
「図工でたんぽが必要になりますのでおうちで用意お願いします」とありました。

た、たんぽ?
何それ?
たんぽが何か分からず、そんな単語聞いたこともないし
娘に何に使うのか?と聞いても
もちろん娘もわからず・・
勝手に想像して作った失敗作も含め
いろいろ調べて作りましたのでご紹介しますね。
※お急ぎの方は目次より「簡単!たんぽの作り方完成形」をご覧ください。
そもそも「たんぽ」って何?
それにしてもたんぽって名前どうなの?
ちょっと調べてみました
タンポは、拓本を採るときに墨をつけて叩く道具である。書や絵をかくときの筆に当たる。漢字では「短穂」あるいは「打包」と書く。後述するように綿を丸めて球状にするところから、語感が似たタンポン(綿球)に由来する語と誤解されることがあるが、両者の間には特に関係ない。(Wikipediaより)



だそうです。
なるほどです。
たんぽの作り方を読んで形を想像する
学校からのお知らせには作り方が一応書いてありました。



???
何となく形は想像できるけど・・
てるてる坊主状態の団子みたい?
いらない布はいくらでもあるけど中に詰める綿(わた)は買ってこないと・・
ここで私のめんどくさがりが出てわざわざ買いに行くのがめんどくさくなり
「中も布を切り刻んで詰めればいいんじゃないの?」
ということにしてしまいました。
たんぽの材料を自己流で作ってみた結果
でも、布を切り刻みだしてから後悔しました。
直径10cmの団子状にするための切り刻んだ布(切り刻まないとうまく団子状に詰まらない)の量は大量でした。
ハサミを持つ手が痛くなるほど・・
時間もかかった・・
それに大量の布が詰まっているので



お、重い・・
ずっしりって感じ
(重くて当たり前・・)
なんとかかんとか団子状にして娘に「どうや!」と渡しておきました。
失敗作たんぽを娘が図工で使った感想
そして実際に図工で使って学校から帰ってきたら



おかあさん!
たんぽ、ぜんぜんあかんかったわ!
と苦情
たんぽをどう使ったのかと聞くと
絵の具をたんぽに吸わせて紙にポンポンと押し付けて色を付ける作業だそうです。
でも、たんぽに絵の具が全く吸い込まなかったそうです。
その上重いし・・



う~~ん・・
中が布だったからかなぁ
(その通り!)
他の子のたんぽはちゃんと中は綿(わた)だったそうです。
みんなえらいなぁ
結局、そのたんぽは使えないので先生が用意していたたんぽをもらったそうです。
悪かったねぇ娘よ・・
簡単!たんぽの作り方完成形
そんな事があったので小学2年生になってからのある日
学校から持って帰ってきた予定表の持ち物欄にまた「たんぽ」と書いてありました。



今度はまかせて!
と娘にはりきって宣言しました。
前回の失敗をふまえて今度はたんぽの中は綿にすることにしました。
(普通です)
たんぽの完成形作り方
・綿(100均ショップに売っています)20センチ角くらい
・布またはガーゼでもいいですよ
・輪ゴム
1.着られなくなったTシャツを切り
(1個分は前後どちらかの見頃の4分の1程の大きさに四角く切ります)
2.綿をギュッと包んで輪ゴムでギュギュっと縛り付ける
3.あまっている部分の布を切り取る
↑今回の成功たんぽ
今度はパフパフした軽いたんぽでいい感じにできあがりました!
見た目は前回の失敗作と変わりませんが重さが全然違う!
(当たり前)
しかもあっという間にできました。
今回はうまく絵の具を吸い込んで使いやすかったらしく
娘もよろこんでいました。



たんぽ作りはまかせといて!
といきまいていましたが
その後たんぽが必要になることはなかったです・・
たんぽ作りの参考にしていただけるとうれしいです♪